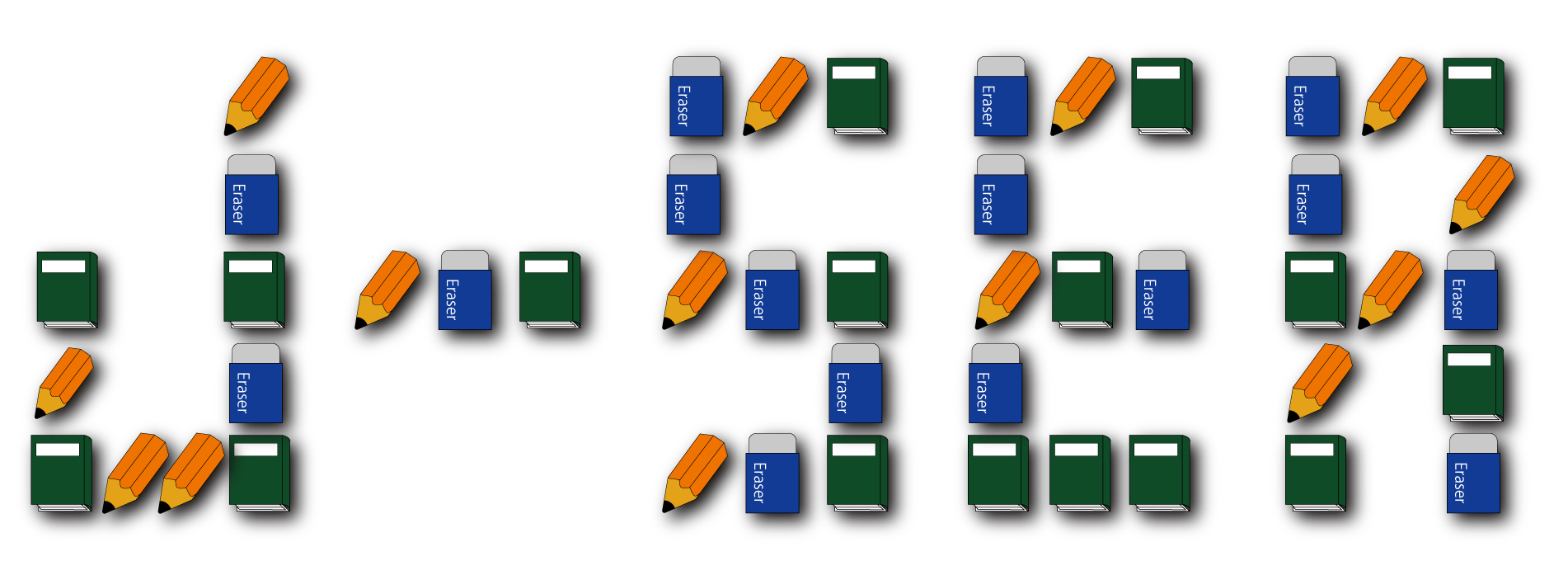このたび学術英語学会では,大阪市立大学大学院教授山崎孝史先生をアカデミック・アドヴァイザーにお迎えすることとなりました。
現代日本における「研究者のための英語」という大きな課題に取り組む本学会としては,自然科学分野とあわせて人文社会科学分野の研究者の取り組みを十分に把握する必要があります。米国での学位取得,豊富な在外研究,英文ジャーナルの発刊等,文字通り国際的舞台でご活躍されている山崎先生からいただく御指導,御助言は,今後の学会の展望を大きく広げるものと期待されます。
ご略歴と,本学会のために御寄稿いただいたメッセージをここに掲載させていただきます。

略歴
京都市生まれ。京都大学大学院博士課程を中退し、京都大学文学部に就職。山口県立大学国際文化学部転任後、フルブライト奨学生(大学院研究)に採用され、米国コロラド大学地理学部大学院に入学。2001年に大阪市立大学大学院文学研究科に就職し、2004年にPh.D取得。現在は文学研究科教授ならびに学術情報総合センター所長(大学図書館長)。
専門は政治地理学、沖縄研究であるものの、2006年に文学研究科のCOEプログラムに関わる英語プレゼンテーションのトレーニングプログラムを構築し、2007年から4年間、大学院GPプログラムとして英語による発信力向上を目指す「インターナショナルスクール」事業の各種プログラムの構築と運営に関わる。そこでは、自らの経験をベースに、英語口頭発表、国際交流プログラム、英語ライティングの各セミナーにおいて自らも講師として多くの大学院生を指導した。
専門分野においても、国際政治学会「政治・文化地理学研究委員会」共同委員長、国際地理学連合京都地域会議「コミッション委員会」副委員長、国際地理学連合「政治地理委員会」共同委員長を歴任し、サンチアゴ、マドリッド、京都、モスクワ、北京での会議・セッション運営や基調講演を担う。また、政治地理学分野での代表的国際雑誌Political Geography (Elsevier)およびGeopolitics (Taylor & Francis)の編集委員を務め、多くの論文を査読するとともに、自らの論文も公表している。
2010年には、文学研究科の関係教員・大学院生による研究成果の日英翻訳と国際発信を促進するために、英語によるオンライン・オープンアクセスジャーナルUrbanScopeを自ら創刊した。さらに、大学図書館長という立場から、全国の大学図書館や国立情報学研究所と連携しながら、国際学術雑誌の購読と研究公表手段の最適化、機関リポジトリの利用拡大などオープンサイエンス化の促進などの課題にも取り組む。
著書に『政治・空間・場所―「政治の地理学」にむけて[改訂版]』(ナカニシヤ出版、2013年)、共著書に『領土という病―国境ナショナリズムへの処方箋』(北海道大学出版会、2014年)、論文に” ’The US militarization of a ‘host’ civilian society: the case of post-war Okinawa, Japan’ (S. Kirsch and C. Flint eds. Reconstructing Conflict: Integrating War and Post-War Geographies. Ashgate, 2011)、’The re-institutionalization of island identities: the “textbook fight” in the Yaeyama Islands, Japan’.(D. Kaplan and G. Herb eds. Scaling Identities. Rowman & Littlefield, forthcoming)など。
メッセージ
私にとって学術英語のスキルは誰かから教授されたものではなく、英会話の独習、国際会議への出席、国際的な奨学金への応募、米国留学経験、英語論文執筆といった個人的な経験から蓄積されたものです。よって、これらのスキルは体系化されたものでは全くなかったのですが、勤務校における大学院GPプログラムという教育実践を通して、「移転」可能な知識の体系として再構築するよう努めてきました。しかし、それでも個人の技量の「伝授」という次元を超えることは難しく、私が構築した各種プログラムも担当者が交代するにつれ、私が当初意図したような形では継承されなくなっていきました。その一方で、大学教員による「手作り」プログラムよりも、洗練され、商品化されたプログラムを語学系の企業が提供(販売)するようにもなりました。
しかし、そうしたプログラムは需要に応じた商品であることを避けられず、自然科学から人文・社会科学至る多様な分野からなる大学教員や若手研究者のニーズに応じたものとも言い切れません。またそれは「商品」である以上、公共財として蓄積されていく知識・技能ではなく、学内に「移転」されるものでは必ずしもありません。そうした観点から考えると、大学人の側が、企業のノウハウも取り入れながら、公共財としての学術英語の在り方を議論し、その成果を蓄積・普及していく努力を続ける必要があると考えられます。
また、昨今の英語商業雑誌の寡占化と為替変動や課税と関わる高額化は、公共財としての学術知識の生産・流通・蓄積に大きな負の影響を及ぼしています。私たちの知的資源は高等教育経費の削減とも相まって縮小化しつつあります。そうした中での行き過ぎた商業誌への依存は、特定の出版社による知識の生産と流通の独占を生み出し、本来公費によって公共のために行なわれた研究が公的に享受されない事態も生み出しかねません。特定の国際学術出版社が大学に雑誌購読を継続させるために、自誌投稿を促すライティングセミナーを開催することも、学術英語スキルの普及にはつながるかもしれませんが、そうしたスキル普及(投稿者養成)まで営利活動の一環に取り込まれる事態には眉を顰めざるを得ません。
その意味でも、大学関係者が中心となり、自らの経験と知見を持ちより、より公共的な学術英語の確立・活用・普及に貢献せんとする本学会の意義は小さからざるものがあると言えるでしょう。本学会の更なる発展を応援したいと思います。
石川慎一郎先生(アカデミック・アドヴァイザー)のご紹介
このたび学術英語学会では,神戸大学大学院教授石川慎一郎先生をアカデミック・アドヴァイザーにお迎えすることとなりました。
日本におけるコーパス言語学の第一人者である石川先生は優れた研究業績をあげてこられ,また大学院における熱心な指導でも有名です。英語のライティングは多くの研究者にとって最大の関心事であることは言うまでもありませんが,本学会は,コーパス言語学から得られる知見がライティングの向上にきわめて有効であることに着目し,言語研究の成果をいち早く「研究者のための英語」に役立てようと試みております。石川先生からいただく御指導,御助言は,今後,学会が推進する「学術英語」の研究およびライティング・セミナー等の企画に大きな助けになるものと期待されます。
ご略歴と,本学会のために御寄稿いただいたメッセージをここに掲載させていただきます。
(ご略歴)
神戸市出身。神戸大学文学部卒業。神戸大学文学研究科/岡山大学文化科学研究科修了。博士(文学)。静岡県立大学,広島国際大学を経て,現在,神戸大学全学基盤系教育基盤域教授。専門は応用言語学。主著として,『英語コーパスと言語教育』(大修館書店,2008),『言語研究のための統計入門』(くろしお出版,2010), Corpora and Language Technologies in Teaching, Learning and Research(University of Strathclyde Publishing, 2011),『ベーシック コーパス言語学』(ひつじ書房,2012),『日本語教育のためのコーパス調査入門』(くろしお出版,2012),『言語研究と統計的アプローチ』(金星堂,2016),『ベーシック応用言語学』(ひつじ書房,近刊)ほか。コーパス言語学や実験心理学などの科学的・実証的アプローチに基づく言語研究の業績によって,大学英語教育学会学術賞,全国英語教育学会学会賞,中部地区英語教育学会学会賞他を受賞。
(メッセージ)
応用言語学の領域においても,専門目的のための英語(English for Specific Purposes)と,一般目的のための英語(English for General Purposes)をつなぐ概念として,広義の学術英語(English for Academic Purposes)への関心が高まっています。しかし,何をもって学術英語と呼ぶのか,学術英語の示差的特徴は言語学的にどのように同定できるのか,学術英語教育と一般英語教育はどのように切り分けられるのかなど,未だ完全には解明されていない問題も多く残されています。今後,応用言語学がこの点について新たな知見を得ようとするならば,応用言語学者の狭いコミュニティを抜け出て,幅広い学術分野と交流することが不可欠になると言えるでしょう。人文系の研究者と自然系の研究者がそれぞれの背景や見識をふまえつつ,学術英語の諸相を共に議論できる稀有な場として,学術英語学会のますますのご発展を期待しています。